先日、X(旧Twitter)で、日本円のステーブルコインJPYCを「暗号資産」と投稿したところ、「JPYCは暗号資産ではなく、電子決済手段です」と丁寧なご指摘をいただきました。

ステーブルコインとは、価格の安定を目指し、米ドルなどの法定通貨に価値が連動するように作られたデジタル通貨ことなんだよ。
一瞬、頭が真っ白になりかけました。
「え、暗号資産じゃないの?」
多くの方が、今、私と同じように感じたのではないでしょうか。

暗号資産ではないという出来事をきっかけに、ひとつの大きな疑問が沸き上がりました。
では、私たちがステラネットワーク上で利用しているUSDCのようなステーブルコインは、一体全体、何に分類されるのだろう?
この記事では、ステラネットワーク上で利用しているUSDCのようなステーブルコインが何に分類されるのかという疑問と、日本の法律における「暗号資産」と「電子決済手段」の決定的な違いを、ステラネットワークの トークン、 yUSDCを中心に、紹介していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたも自信を持って、「暗号資産」と「電子決済手段」を使い分けられるようになっているはずです。
「暗号資産」と「電子決済手段」の決定的な違い

「暗号資産」と「電子決済手段」の違いを理解する上で最も重要なのが、2023年6月に施行された改正資金決済法によって、日本の法律がこれらのデジタル通貨をどう定義し、区別したか、という点なのです。
改正資金決済法によって、これまで曖昧だったデジタル通貨の定義がはっきりと分けられました。
具体的には、「暗号資産」と、新たに登場した「電子決済手段」という2つのカテゴリーに分類されたのです。
1. 暗号資産とは、価値が保証されないデジタル資産

暗号資産の代表例としては、 デジタルゴールドのビットコイン(BTC)、ワールドコンピュータと言われてるイーサリアム(ETH)、送金用暗号資産のステラルーメン(XLM)等があります。
暗号資産の3つの特徴
- 価値が特定の法定通貨に連動していない
- 価値の変動が激しい
- 投資目的での利用等が多い
※「投資」は長期的な視点で資産の成長を期待するのに対し、「投機」は短期的な価格変動から利益を得ることを目指します。
価値の非連動性: 価値が特定の法定通貨(円やドル)に連動していません。
価値の変動性: ビットコインのように特定の発行者や管理者が存在しない「非中央集権的」なものもあれば、ステラルーメンのように管理主体が存在する「中央集権的」なものもあります。
しかし、いずれも価値は純粋に市場の需要と供給によって決まります。
市場の評価が直接価値に反映されるため、時に激しい価値変動が起こります。

カンタンにたとえると、1,000円のランチ代を支払う時に、貨幣価値が支払いの瞬間には1,200円分になっていたり、逆に800円分の価値に下がっていたりするのでは、日常の決済手段としては使いにくい側面があります。
主な用途: 決済手段としてだけでなく、価値の保存や投機・投資の対象として見られることが多いのが特徴です。
2. 電子決済手段とは、価値が安定したデジタル決済手段

電子決済手段の代表例としては、アメリカのドル通貨に連動したUSDC、USDT、日本円に連動したJPYCなどがあげられます。
ここでは、特に代表的なUSDC、USDT を例に、電子決済手段が持つ3つのおおきな特徴をみていきましょう。
- 価値が特定の法定通貨に連動している
- 価値の変動が少ない
- 国際送金目的等での利用が多い
※USDCは米国のCircle社が発行し、準備金の透明性が高いことで知られていますのに対し、USDTはTether社が発行しており、その準備金については様々な議論があります。
価値の連動性:(価値が安定している)電子決済手段は、その価値が法定通貨(主に米ドル)に連動(ペグ)するように設計されています。たとえば、「1USDC≒ 1ドル」のように価値が安定しているのが最大の特徴です。
明確な発行者の存在: 価値を担保するために、Circle社(USDCの発行者)のような明確な管理者が存在します。
発行者は、発行した総額と同等以上の資産(現金や短期国債など)を準備金として保有することで、価値を裏付しています。
主な用途:暗号資産の価格変動リスクを避けるための一時的な避難先として、また、国際送金など、迅速かつ安価な「決済」手段としての利用が主目的です。

日本の新しい法律(改正資金決済法)は、利用者の保護や資産洗浄対策を強化する目的で、アメリカのドル通貨に連動したUSDC、USDT、日本円に連動したJPYCなどを「暗号資産」とは別のカテゴリーとして明確に定義されました。
※資産洗浄とは、不正に得た資産の出所を分からなくすることを言います。
ステラネットワーク上のyUSDC、日本での分類では電子決済手段となる。
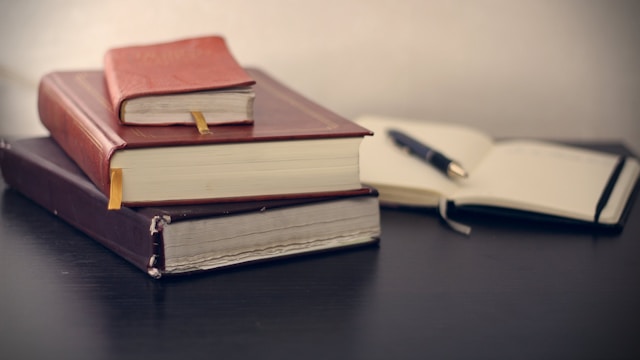
ステラネットワーク上で利用する「yUSDC」は、いったいどのようなものなのでしょうか?
「yUSDC」は、Circle社が発行する米ドルステーブルコイン「USDC」を基にした「橋渡し(ブリッジ)」したトークンです。
トークンとは、たとえるとゲームセンターで使う専用コインをイメージすると、とても分かりやすい。
日本円をゲームセンターのコインに両替すると、そのゲームセンター内でだけ使えるようになりますよね。
暗号資産の世界における「トークン」も、ゲームセンターのコインと似たような「特定のサービスやネットワーク上で利用できる、価値の証明書」のことなのです。

ちなみに、USDCを発行しているCircle社は、2021年から公式にステラネットワークに対応しています。
これにより、他のネットワーク利用せずに、ステラネットワーク上で直接USDCを発行・利用することが可能になりました。
ステラネットワークの「速くて安い」という特徴を活かした代表的な例が、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)による難民支援プログラム「Stellar Aid Assist」です。
ウクライナの紛争で影響を受けた人々に対し、支援金がUSDCでスマートフォンに直接届けられま
した。

受け取った人々は、銀行口座がなくても、世界中にあるマネーグラムの拠点(世界中に店舗を持つ国際送金サービス)でUSDCを現地通貨に換金することできました。
まさに、ステラネットワークの技術が、人道支援の現場で大きな力を発揮した事例です
電子決済手段(ステーブルコイン)がもたらす3つのメリット

USDCのようなステーブルコインは、単なるデジタルな通貨というだけでなく、具体的に私たちの生活にどのようなメリットがあるのでしょうか。
暗号資産の特性と、法定通貨の安定性をもつステーブルコインは、私たちの日常に、これまで想像もしなかったような利便性や可能性をもたらすかもしれません。
ここからは、そんなステーブルコインが、私たちの身近な生活シーンでどのように役立つのか、具体的な例をいくつかご紹介していきましょう。
- 海外送金の手数料が減り、カンタンになる。
- 海外オンラインサイトの買い物が手軽になる。
- 暗号資産の避難場所となる。
1. 海外への送金が「速く、安く」なる
海外に送金する場合、銀行からの国際送金サービスを利用します。これには数千円の手数料と、着金までに数日かかるのが当たり前。
ところが、ステラネットワークのUSDCのようなステーブルコインを利用した場合の送金手数料はほんの数円程度、着金までにかかる時間もわずか数秒です。まさに、メールを送るような感覚で、価値を世界中に届けられるようになるのです。
2. 海外サイトでの買い物がもっと手軽に
日本に欲しい品物がなくて海外の通販で買い物をする時、クレジットカードでドル建ての決済をすると、後日、カード会社が定めた為替レートに、海外利用手数料(購入金額の2%〜4%程度) が上乗せされて請求されます。
もし、ステーブルコインUSDCが利用可能であれば、あなたの持っているUSDCで支払うことができます。
これにより、不透明な為替手数料を心配することなく、よりお得に買い物を楽しむことができます。
3. 資産の「安全な避難場所」として
暗号資産の世界は、価値の変動が非常に激しいのが特徴です。
暗号資産市場が不安定になったとき、資産の避難先として多くの投資家は、保有しているビットコイン(BTC)やステラルーメン(XLM)などを一旦売却し、価値が安定しているステーブルコインに交換します。
ステーブルコインを持っていることで、暗号資産市場が暴落している間も資産価値の目減りを最小限に抑え、冷静に次の投資機会を待つことができるのです。
ステーブルコインは、荒波の暗号資産市場における「安全な港」のような役割を果たします。
もっと知りたい!ステーブルコインQ&A

最後に、この記事を読んでくださった方が思う疑問について、Q&A形式でお答えします。
質問1. なぜ、わざわざステーブルコインが必要なのですか?
回答1. 暗号資産の価値変動の大きさを解決するためです。
ビットコインのように価値が常に変動するものでは、日常の支払いには使いにくい場面が多くあります。
ステーブルコインは、その価値を法定通貨に連動させることで「価値の安定性」を実現し、ネットワーク技術が持つ「速くて安い決済」というメリットを、誰もが安心して利用できるようにするために生まれました。
質問2. 日本円に連動したステーブルコインはありますか?
回答2. はい、あります。この記事のきっかけとなったJPYCもその一つですし、他にもいくつかのプロジェクトが日本円連動のステーブルコインを発行・開発しています。
2023年の法改正により、日本国内でもステーブルコインの発行や流通がしやすくなる環境が整ったため、今後はさらに種類が増えていくと予想されます。
質問3. 「電子決済手段」は「暗号資産」より安全と言えますか?
回答3. 「価格変動リスク」という点においては、比較的安全と言えます。
しかし、100%リスク回避できるというわけではありません。例えば、発行者の信用リスク(発行会社が倒産するなど)や、以前、USDTが起こした裏付けとなる資産が不透明になったり、スマートコントラクトのバグといった技術的なリスクは存在します。
法律で規制されているとはいえ、利用する際は、ステーブルコインがどのような仕組みで価値を担保しているのか、信頼できる発行者なのかを、ご自身で確認することが大切です。
知らないと損!ステーブルコインと「yUSDC」は暗号資産じゃない?法律上の正しい分類と使い方のまとめ
暗号資産の技術的な仕組みと法率的な分類は、必ずしもイコールではないということが、浮き彫りになりました。
【暗号資産】
- 該当: XLM, BTC, ETH など
- 見分け方: 法定通貨の裏付けがなく、価格が大きく変動する。
【電子決済手段(ステーブルコイン)】
- 該当: yUSDC, USDC など
- 見分け方: 法定通貨の裏付けがあり、価格が安定している。
SNS等で発信する際、ステラネットワーク上のyUSDCのようなステーブルコインを指す場合は、「暗号資産」という言葉を避け、「ステーブルコイン」、より正確性を期すなら「電子決済手段」と使い分けることで、より正確な知識を伝えることができます。
法律や規制は、私たちの資産を守るために存在します。
複雑で面倒に感じることもありますが、正しく理解することで、より安全に、デジタル資産と付き合っていくことができます。
ではでは
今回はこのへんで
ココまで読んでいただきありがとうございます。
ごきげんよ〜



コメント